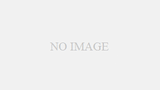生まれてから数か月は、よく飲みよく寝て穏やかに過ごしていました。
しかし、6か月頃から夜に激しく泣くことが増えてきました。
最初は夕方に寝てしまい、夜寝つけずに
激しく泣いていました。
スポンサードリンク
夜泣きしないように昼寝の時間を調整し寝付くようになったものの

睡眠リズムを整えるために離乳食の時間をずらし、昼寝の時間を調整し、寝すぎないように起こし、という対策を取りました。
このような生活を行うと時間に追われ、この時間に何をしなければいけないかと時計とのにらめっこばかり、子供の気持ちやリズムなんてまるで無視のような状態でした。
時間通りに動いてみり、今日はいいや、と適当にしてみたりとそんな生活を1か月ほど続けると成長の証なのか寝つけず泣くことはなくなりました。
安心したのも束の間、ここからが本当の夜泣きとの戦いの始まりでした。
赤ちゃんが夜泣きしても泣かせっぱなしの無力さに涙

寝付いた娘をベッドに残し、自分の用事を済ませてから眠りにつく私ですが、うとうとし始めた23:30頃になるとぐずぐずと泣き始まります。
そうなるとまず、娘の好きなオルゴール音の音楽をかけトントンしたりお腹をさすったりします。
これで1時間くらいはすやすやと寝てくれました。
2人で眠りに落ちた1:00頃になると今度は娘の激しい鳴き声で私が目を覚まします。
泣いてすぐに抱っこをすると癖になり、泣けば抱いてもらえると思って激しく泣くようになると聞いたことがあり、抱かずにいれば落ち着くのだと自分に言い聞かせちょっと触ったり音楽をかけたり、電気を暗くしたりと試していました。
しかし、このやり方で効果を感じたことがなくむしろ激しく泣き続け、ほかの家族や近所に迷惑ではないかとハラハラし、いつになったら泣き止むのかとイライラし、いつか静かになると何もせずにいる自分に呆れ、涙が出てきました。
そんな時、知り合いの方に
「大人だって何となく眠れない夜とか、寝たくない時とかあるでしょう。
だから家は夜中に泣いたら起こしちゃうの。
おなかを満たして、遊んで満足すればまた寝るから。」
と笑って話されたことをきっかけに、夜泣きの対応について改めて考え直しました。
スポンサードリンク
赤ちゃんの夜泣きの付き合い方を考え直してみた所

その後は、激しく泣き始めたら豆電気をつけて音楽を流しベッドから降ります。
激しい泣きが落ち着くまで十分に抱っこしてからおむつ交換をしてミルクをあげます。
ミルクの量が気になるときは白湯をあげることもあります。
おなかを満たした後は
朝まで遊んでもいいんだよ、
という気持ちで遊び時間の始まりです。
激しく遊んでしまうと興奮してしまい目がぎらぎらしてしまいますが、ふかふかのぬいぐるみを使ってスキンシップを図ったり、毛布にくるんでくすぐったり、抱っこでゆらゆらしながら壁にかけてある物に触れたりゆったりと遊びます。
日中はマットの上におもちゃを並べてゴロゴロして遊ぶのも、ラックに座って一人遊びをするのも好きですが、夜はやはり人恋しいのか一人遊びでは激しく泣いてしまう時がほとんどなので、なるべく肌に触れて遊びます。
こちらがゆったりと対応すると娘にも伝わるようで再入眠するのも早いように感じます。
わかってはいても、次の日のことや深夜という時間帯のことを考え焦ってしまうことも多々ありイライラが爆発しそうな時は涙が出ます。
毎回うまくいくわけではないですが、娘はこういう子なんだと受け入れること、夜泣きが永遠に続くことはなくずっと寝ないこともないということを常に頭の片隅に置くよう心がけています。
寝たくないなら寝なければいい、
起きていないなら起きていればいい、
次の日のことは次の日に考える、
そういったあきらめに似た受容が大切なんだと強く思いました。
そして、そんな時に話を聞いてくれる誰かがいると、負の感情が娘に向かうこともなく自分の中で区切りをつけられます。
同じ悩みを持つ人の存在を知ることも、私にとっては強い味方となりました。
スポンサードリンク