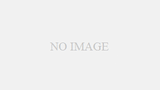赤ちゃんが生まれた後の手続きにも、それぞれ決められた期間があります。
また、名前を付ける人や付け方にも、一般的な感覚から、地域によっての考えなど、様々あって迷うことも多いと思います。
ここでは、一般的な基準を書いていこうと思います。
赤ちゃんの名前は誰がつけるの?

特に誰それが決めなくてはいけない、という決まりはありません。
大体の場合は両親がつけます。
ただし、田舎のほうだったりすると、
「こういうものは祖父母がつけるべき」
「お寺さんに聞いて、いい名前の候補を考えてもらうべき」
「父親が男の子、母親が女の子の名前をつけるべき」
等々のこだわりがあるところも多いようです。
赤ちゃんの誕生はとても喜ばしいことなので、親族もそろって名前を考えることが楽しみなようですね。
ですが、あくまでも生みの親がつけた名前が一番ではないかと私は思います。
例えば、お寺の和尚さんから難しい理由のある名前をつけてもらったとして、将来自分の子供に名前の意味を聞かれたときに問題なくこたえられるでしょうか?
それに、どれだけ立派な名前でも、自分たちがつけた、という充実感や喜びが感じられないのは
寂しいと思います。
もし、親族の中で、両親以外の人がつける可能性のある場合は、「自分たちで名前をつけたい」ということをしこりを作らない様に伝えることも検討した方がいいかもしれません。
赤ちゃんの名前はどうやって決めるの?

名前の付け方ですが、これは実に色々とあります。
妊婦さんが出産雑誌の名前の冊子を読んで考える、というのをよく聞きますが、それだけでは決まりません。
一般的に考えるポイントを以下に挙げていこうと思います。
・呼び名・響き
・名前の意味
・姓名判断
・画数
これらを全て守ってつける必要はありませんが、どれも名付けるのに重要なポイントとなります
例えば、呼び名や響きは、呼ぶ側呼ばれる側も読みやすいものがいいですよね。
あまり個性的だと将来子供自身が不快に感じるかもしれません。
また、名前に付けた意味も、子供に聞かれたらきちんと説明してあげたいですよね。
親自身でさえ、難しくてよくわからないのは避けた方が無難でしょう。
姓名診断というのは、簡単に言えば、その人の運勢を決めるものです。
その人の性格・人格や、将来の適職、運周りやかかりやすい病気など、どれがその赤ちゃんにあっているかじっくり考える必要があります。
気にしない人も増えてきているようですが、一生の運勢を決めるものとして、考えておくのもいいかもしれません。
画数は、特別これが良いというものはなく、人それぞれなのですが、あまり字数が多すぎたり、簡単すぎるものも良くはないでしょう。
「小学校低学年までに習う漢字を使う」というかんがえもよく聞きます。
また、苗字とのバランスも考えた方がいいかもしれません。
苗字が長くて書きづらいのに名前まで書きづらいと大変ですよね。
あくまでも使用するのは子供自身、という配慮もした方がいいでしょう。
名前についての考え方はたくさんあるので、
夫婦でじっくり考えることが一番なのではないでしょうか。
赤ちゃんの名前はいつまでに決めるの?

初めて公の場で名前を出すのが、出生届になります。
これは、生後14日以内に提出することが定められており、ここに間に合わせて名前を考えるべきです。
必ずしもその期間内に考えておかなければいけないというわけではありませんが、名前の所を白紙で提出することになってしまいます。
なるべく、出産前までに決めておくのが良いのではないでしょうか。
まとめ
大事な赤ちゃんの名前をつけるのには、誰もがとても頭を悩ませます。
日本には外国のような定型的な名前がないので、一から意味合いやバランスなどを考えなくてはいけないので、中々にハードルの高いイベントですよね。
全てを詰め込んだ名前をつけるというのは難しい話です。
最終的には、「これでいい!」と思える名前が一番だと思うのです。
そのためにも、どういったものを考える必要があるのか、よく調べておきましょう。